【野々市】災害に備える、福祉と防災の交差点
- 中村せせらぎ
- 2025年9月13日
- 読了時間: 2分
9月13日(土)は、災害と福祉に向き合う一日でした。
まずは、防災倉庫の備品チェックと、9月28日に予定されている防災訓練の打ち合わせ。市民の安全を守るための準備は、地道な確認と連携から始まります。
その後、社会福祉協議会による「社会福祉功労者表彰贈呈式」に出席。知り合いの方が表彰されていて、福祉の現場がぐっと身近に感じられました。地域の支え合いの力を、改めて実感する時間でした。
🎤講演「あなたとあなたの家族を守るために」その後、日本防災士会理事であり香川大学危機管理先端教育センターの高橋真理さんによる講演を聴講。災害ボランティアの歴史が語られ、1923年の関東大震災では帝国大学の学生が救援活動に参加した記録があること、1995年の阪神・淡路大震災では延べ137万人が参加し「ボランティア元年」と呼ばれたこと、そして2011年の東日本大震災では全国196カ所に災害ボランティアセンターが設置され、約550万人が活動したことが紹介されました。令和6年能登半島地震では、2025年8月末時点で18万人以上が参加されたとの報告もありました。
印象的だったのは、「災害時に行政に頼ることはやめよう。行政には行政にしかできないことを任せ、自分でできることは自分でやる」という言葉。市民一人ひとりの備えと行動が、地域の力になります。
「ふくしフェス2025」では、VR防災訓練を体験。専用メガネを通して地震の揺れを体感し、余震の後に続く長く大きな揺れに思わずバーチャル映像の机にしがみついてしまいました。
また、車いす操作体験では、押す側と乗る側で感じ方がまったく違うことを実感。わずかな段差でも、乗っている方にとっては前のめりになる危険があり、細やかな配慮が必要だと学びました。
さらに、手足に重りをつけ、視界が不自由になるメガネをかけての歩行体験では、ほんとうに心細く、移動の不安を肌で感じました。
🌱災害に思いを馳せる一日
防災と福祉は、どちらも「誰かの命と暮らしを守る」ための営み。今日の体験を通して、災害時の行動や支援のあり方を、より深く考えることができました。
市民の声と行動が、地域の安全と支え合いを育てていきます。これからも、備えと学びを重ねていきたいと思います。



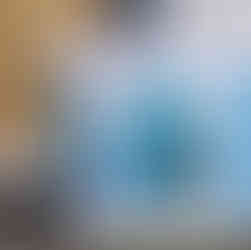


















コメント