【野々市】命を支える朝と午後~野々市の暮らしの中で
- 中村せせらぎ
- 8月24日
- 読了時間: 2分
更新日:8月26日
8月24日(日)今朝もお寺の前では、恒例の朝市が開催されました。出店しているのは、下林地区のお年寄りたち。自ら育てたナス、オクラ、金時草などの新鮮な野菜が並びます。野菜のみの素朴な市ですが、土の香りと人のぬくもりが感じられる、野々市らしい朝の風景です。
午後は、市内で開催された「こどものSOS受け方講座」に参加しました。対象は私たち大人~保護者、教職員、地域の支援者。講師は、石川県こころの健康センター所長の角田雅彦先生です。
🧠こどもたちのSOSに、どう応えるかがテーマ
昨年、自殺で命を落とした中学生は全国で529人。過去最多です。
特に、夏休み明けは子どもの自殺が増える時期。これは偶然ではありません。
今月、視察先の川崎市「子ども夢パーク」で、西野元所長が語っていた言葉が思い出されます。「学校に行かないことが、子どもたちの重しになる場合がある」 学校に行かない選択をした子どもたちだけでなく、子どもたちは、言葉にならない形でSOSを出しています。
私たち大人は、そのサインを見逃してはいけません。
角田先生は、子どもの命を守るために必要な4つの行動を教えてくださいました。
🛟大人ができること:
1. 気づく
2. 話を聴く
3. つなぐ(専門機関や信頼できる人へ)
4. 見守る
「死にたい」と言われたら、真剣に話を聴くこと。その子は、あなたを選んで打ち明けているのです。「死なない約束」ができるといい——その言葉が胸に残りました。
🧩ゲートキーパーとしての私たち
講義では「ゲートキーパー(GK)」という言葉が紹介されました。
命の門番として、周囲の変化に気づき、声をかけ、支援につなぐ人のことです。
• 「相談できる相手は?」という調査では、
友だち(82%)、家族(51%)、先生(23%)という結果。
子どもは身近な人にSOSを出していますが、もっと大人に話してほしいと先生は言います。
• しかし、日本の子どもは「助けて」となかなか言えません。
「死にたい」などと言えない子どもたちです
だからこそ、私たち大人が気づき、寄り添う必要があります。
🌱地域の営みが命を支える
朝市で並ぶ野菜は、下林のお年寄りが丹精込めて育てたもの。
その手間と愛情は、地域の命を支える営みそのものです。
午後の講座で学んだのは、子どもたちの命を守るために、私たち大人ができること。
「気づく」「聴く」「つなぐ」「見守る」──この4つの行動を、日常の中で実践していきたいと思います。
命の重みを受け止める覚悟と、地域のぬくもりをつなげる力。
野々市の暮らしの中に、確かにその両方があると感じた一日でした。












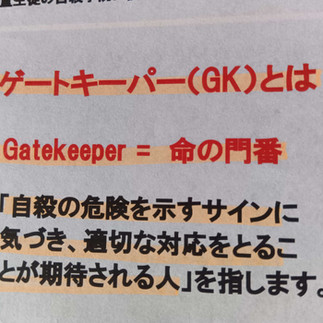


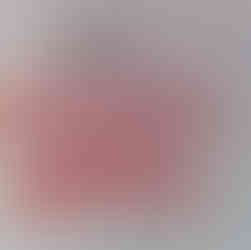






コメント