【淡路市】地域の記憶と備えが命を守る力に~北淡震災記念公園
- 中村せせらぎ
- 2025年10月30日
- 読了時間: 2分
10月30日(木) 視察2日目は、明石海峡大橋を渡って淡路島へ。訪れたのは、阪神・淡路大震災の震源地に近い淡路市にある「北淡震災記念公園・野島断層保存館」です。
ご説明くださったのは、震災語り部であり旧北淡町職員の富永登志也さん。地震発生当時の状況や、地域の対応、そして今に続く記憶の継承について、現場の声を交えてお話しいただきました。
1995年1月17日午前5時46分に発生した「阪神・淡路大震災」。旧北淡町では、最大右横ズレ210cm、隆起130cmという地表のズレが確認されました。この野島断層は現在、国の天然記念物として指定され、185mにわたり保存・展示されています。地震の力を目の当たりにしながら、自然の脅威と向き合う大切さを改めて感じました。
震災当時、人口約11,000人の町で亡くなられた方は39名。早朝6時半には災害対策本部が設置され、昼過ぎには生き埋めとなった300人全員が救出されたとのこと。消防団員565人に加え、OB500人が活動し、人口の約1割が消防団として動いたという事実に、地域の力の大きさを実感しました。「早朝で住民が自宅にいたことが、迅速な対応につながった」との説明も印象的でした。
震災時には最大19か所の避難所が開設され、3,650人が避難。仮設住宅は12か所600戸が整備されました。令和6年の能登半島地震を思いながら、「復興の難しさを痛感している」と語られた富永さんの言葉には、重みがありました。
避難所運営において、自治体職員2名を配置できたのは、10市10町のうちわずか2町のみ。「日頃からやっていた」という言葉が、深く心に残りました。台風時の避難所開設経験があったこと、教育委員会職員が鍵を持ち、各避難所の担当職員名を明確にしていたという事例は、非常に参考になりました。
北淡震災記念公園では、地域の記憶を継承する語り部の力と、日頃の備えが災害対応に直結することを、改めて学ぶことができました。語り部の言葉は、単なる記録ではなく、命を守る知恵として私たちに届きます。
避難所運営においても、教育委員会職員が鍵を持ち、担当職員を明確にしていた事例は、本市の災害体制にも活用できるのではないかと感じました。また、日常的な訓練の重要性を再認識し、今後の防災施策に活かしていきたいと思います。
災害に備えることは「特別なこと」ではなく「日常の延長線上」にあるべきだと感じています。語り継ぐこと、備えること、そして行動すること。これからも市民の皆さんと共に、命を守るまちづくりを進めてまいります。




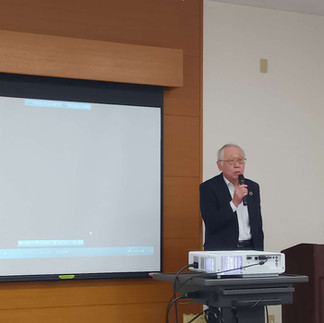



















コメント